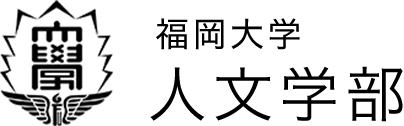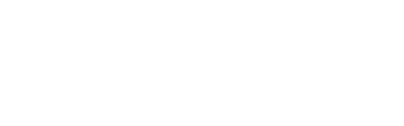東アジア地域言語学科
East Asian Studies
中国・韓国を中心に東アジア地域をとらえた学び
ボーダレスに活躍できる人材を目指す
KEYWORDS
- #東アジア
- #ネイティブに触れたい
- #海外で働きたい
- #アジア文化が好き
- #中国
- #韓国
- #台湾
- #朝鮮
- #映画
- #K-POP
- #韓国語能力試験(TOPIK)
- #ハングル検定
- #中国語検定試験
- #日本語教員
学科トピックス
-

東アジア地域言語学科
2024.04.15
お知らせ
対面式・フレッシャーズセミナー実施
4月10日、前期授業の開始に先立ち学科の新入生対面式が行われました
-

東アジア地域言語学科
2024.04.02
お知らせ
【募集】特別授業『TOPIKⅡ(朝鮮語)対策講座』の受講生募集(4月19日 16:30〆切)
国際センターからのお知らせ
-

東アジア地域言語学科
2024.03.31
お知らせ
東アジア地域言語学科 2024年度新入生の皆さんへ
4月2日(火)9時〜 新入生履修ガイダンス(822教室)
-

東アジア地域言語学科
2024.03.27
報告
韓国コース合同ゼミ合宿を実施
新年度を前に4年生が企画し1泊2日の合宿に行ってきました
-

東アジア地域言語学科
2024.04.15
お知らせ
対面式・フレッシャーズセミナー実施
4月10日、前期授業の開始に先立ち学科の新入生対面式が行われました
-

東アジア地域言語学科
2024.04.02
お知らせ
【募集】特別授業『TOPIKⅡ(朝鮮語)対策講座』の受講生募集(4月19日 16:30〆切)
国際センターからのお知らせ
-

東アジア地域言語学科
2024.03.31
お知らせ
東アジア地域言語学科 2024年度新入生の皆さんへ
4月2日(火)9時〜 新入生履修ガイダンス(822教室)
-

東アジア地域言語学科
2024.03.18
お知らせ
【募集】蔚山大学校(韓国)海外研修参加者募集(4月22日 16:30〆切)
国際センターからのお知らせ
- 東アジア地域言語学科
- 学びのスタイル
- バラエティ豊かな教員
4年間で学ぶこと

東アジア地域言語学科のPOINT
POINT 01

基礎から専門へと積み上げていく、きめ細かな教育
講義形式の学びだけでなく、入門演習(1年次)・基礎演習(2年次)・演習(3・4年次)と、入学時から卒業に至るまで、基礎から専門へと積み上げていく、きめ細かな教育を実施しています。言語はもちろん、中国・韓国という地域に関する専門性をしっかりと身につけることができます。
POINT 02

現地経験が豊富な教授陣
中国語・韓国語のネイティブ教員はもちろん、中国・韓国の現地経験が豊富な教授陣。中国語・韓国語の専門家だけでなく、人文社会学のさまざな地域研究分野(言語・文化・文学・社会・歴史・政治)の専門家から指導を受けられる本学科の教育環境は、国内有数のものと言えます。
POINT 03

交換留学など豊富な学びの機会
海外協定校や国内他大学との交流も含め、さまざまな学びの機会があります。交換留学に挑戦し、中国や韓国の学生だけでなく、中国語・韓国語を学ぶ海外の学生たちとともに学ぶ機会や、中国・韓国から本学に留学している学生たちと交流することもできます。
取得できる資格
- 中学校・高等学校 教諭一種免許(中国語)
- 中学校・高等学校 教諭一種免許(朝鮮語)
- 外国人に日本語を教える日本語教員養成課程(日本語日本文学科)の受講も可能です
卒業後の進路状況
海外で働く人や、旅行、ホテル、金融、サービス、日本語教員、商社、マスコミ、航空関連業、本学や他大学の大学院進学など、様々な分野で活躍をしています。